
| 会期 | 昭和館3階 特別企画展会場 |
| 会場 | 平成12年7月25日(火)~8月27日(日)まで |
| 入場料 | 特別企画展会場への入場は無料(常設展示は有料) |
| 主催 | 昭和館 |
昭和20年まで続いた先の大戦は、人々の生活を大きく変え、社会全体にも様々な影響を及ぼしました。また戦後には経済が著しく混乱し、食糧不足もピークに達します。本展では、当時の国民生活の姿を写した写真を通じて、日中戦争が起こった昭和10年代初頭から、日本経済が再び活気を取り戻す昭和30年頃までの人々の暮らしを社会・家庭・子供といった視点を通じて振り返ります。
写真が持つ「記録性」、そしてそこに写る人々や風景の「表情」に注目し、当時の暮らしや世相を様々に 映している写真によって、戦中戦後の厳しい時代を生きぬいた人々の喜びや悲しみ、希望と絶望を、現代に浮かび上がらせようとするものです。多くの人が戦争について最も深く思いをめぐらす終戦記念日をむかえる8月に、戦中戦後の人々の労苦について、そしてこれからの平和について再考する機会としていただければ幸いです。
このころになるとレコードは広く一般にも浸透していきました。肖像写真の入った人気歌手の歌詞カードで壁面を構成します。
レコード会社大手5社のレコードジャケットや、宣伝に使われたのぼり旗などを展示します。
人権尊重、男女平等、言論・思想・信仰の自由など民主主義に基づく一連の戦後改革は日本の社会に画期的な変化をもたらしました。しかしながら戦争によって国土は荒廃し、焼け野原となった都市部での食糧・住宅事情は特に厳しいもので、戦争によって家族を失った遺族や孤児たちは苦しい生活を余儀なくされました。戦後の混乱とインフレの中、人々はバラック生活を送りながら、また闇市で生活物資を手に入れながら、たくましく生きていました。そして日本経済は、昭和20年代後半になってようやく回復の兆しを見せ始めました。
*会場では毎日、資料映像『人々の姿・終戦そして戦後』(約10分)を上映しています。
期間中、2階広場に戦中戦後の町並みを写す大型写真を設置いたします。記念写真をお試しください。
8月27日まで開催した特別企画展『戦中戦後を生きた人々-時代を記した写真展-』は 、
多くの方々にご観覧いただきました。
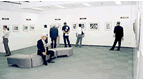

7月30日(日)に2回開催され、好評の内に終了いたしました。

講師に西村建子先生(日本写真家協会会員・二科会写真部会友)をむかえ、
コンパクトカメラの上手な取り方をご指導いただきました。

早速教わった技術を生かして撮影してみました。
8月6日(日)に開催した「牛乳パックで逆さまスコープ!?-ピンホール・カメラを作ってみよう-」が好評だったため、8月13日にも同イベントを追加開催しました。


8月20日(日)に開催した岡井耀毅氏による講演会『戦中戦後を写真家はどう表現したか』では、写真が持つ意味、そして戦時下における写真の特色などをはじめ、岡井氏自身の戦中戦後における体験から様々な事柄についてが語られました。


お問い合わせ
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 昭和館総務部
TEL.03-3222-2577